最近の国会での討論、見たくもないものをさんざん見せつけられてしまいます。これは、日本だけの現象ではなく世界的現象のようです。そんなとき思うのは、人間って進歩しない生き物なんだということです。もちろん、科学技術は驚くほどの勢いで進歩しますが、それと人間の進歩は同じではないでしょう。
そういうときの私にとっての解毒剤は、芸術に触れることです。昨日のETV日曜美術館で「糸から生まれる無限の世界~ヌイ・プロジェクトの挑戦~」を見てあらためてそう思いました。
鹿児島の知的障害者支援施設「しょうぶ学園」の取組を紹介した番組です。その施設では、以前は高級な着物の刺繍を下請けとして、単純な繰り返し作業が得意な利用者にさせていました。しかし、高級な着物です。少しでもスペックにあわなければ指摘され、やり直しさせられます。利用者の表情は、どんどん暗くなっていったそうです。そこで、学園は考え直し、下請け作業ではなく糸を使って各自が好きな刺繍などをつくらせることにしました。すると、表情が見違えるように明るくなり、嬉々として作

業に没頭するようになったそうです。そうして、見事な作品が生まれてきたのです。
彼ら彼女らは、我々が絶対できないような単調な繰り返し作業を、楽しく快適にすることができます。だから、気の遠くなるような手間をかけた作品を生み出すことができます。そして、単調作業に中に作成者のオリジナリティーが自由に発揮されています。
逆に言えば、私たちはそういった作業がなぜできないのかという問いを突き付けられます。面倒くさいから、意味ないから、疲れるから、飽きるから、刺激がないから、他にもっとやるべきことがあるから・・・・、いくらでもできない理由は思いつきます。それが社会化ということなのでしょうか。社会の中で他者と共働して生きていくために、大事な何かを失ってしまっている。障害者は、社会化ができないから「障害者」とされる。でも、いったいどっちが障害者なのか、考えさせられます。
番組の中で作業している女性に、高橋美鈴アナウンサーが握手をもとめました。するとその女性は、とても嬉しそうに握手に応じました。そして、その次にカメラマンにも、照明用の棹を持つスタッフにも次々に握手を求め手を差し出しました。スタッフは撮影中ですから困ったようですが、画面が多少乱れようとも握手に応じました。
普通の人であれば、出演者である高橋アナウンサーと握手すればそれですむと思うでしょう。それが番組の意図ですから。しかし、彼女にとって番組の意図なんて関係ありません。皆と握手したいんです。出演者とスタッフの区別はありません。これが「自由」ということなんだと、観ていて感動しました。
「普通」とされる人間は、状況を読み配慮し周囲から期待される行動を取ろうとします。つまり「自由」ではない。しかし、障害者は自由に本心のおもむくままに行動できる自由な存在です。
正常な人間とは、彼ら彼女ら「障害者」なのではないか。だからこそ、多くの人々の心を打つ作品を創り上げることができるのだと思います。
アール・ブリュットという概念を創出したジャン・デュビュッフェはこう言っています。
「われわれが目の当たりにするのは、作者の衝動のみにつきうごかされ、まったく純粋で生の作者によって、あらゆる局面の全体において新たな価値を見いだされた芸術活動なのだ」
ピカソもマチスも晩年は子供が描くような作品を多数生み出していますが、それも理解できるような気がします。
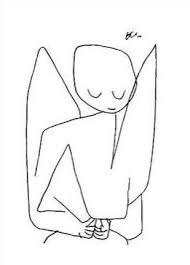
私が携わる人材開発の仕事にも通じることがあります。人材を「開発」するということは、その人が本来持っている能力を発現させるということです。多くの人々は、様々な事情があって発現できなくなってしまっている素晴らしい能力を持っているという前提に立つのです。それは、仕事でも芸術作品でも同じなのです。

コメントする