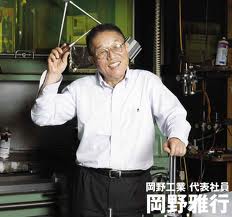動物の行動を観察して人間についての洞察を得る研究には、京都大学をはじめとして長い歴史があります。しかし、アンドロイドを創ることによって人間を知るというアプローチもあったのです。それをやっているのが、大阪大学の石黒浩教授ともいえます。
まだまだ研究途上であり、多くの仮説が生まれてきている段階ですが、それらが面白い。例えば、見かけを自分と全く同じように創ったアンドロイドを前に、人は何を感じるのか。実は人間は自分の姿をそのように立体的に見ることはできません。見ることができるのは鏡を通してだけです。だから、アンドロイドを前にして違和感を持つ。これは自分の声をテープにとって聞くときの違和感と似ています。そう考えると、本当の自分とは?という疑問にぶち当たります。
本書にこうあります。
全ての自己を持つ生き物は、自分を正確に認識しないままに暮らしているのだ。しかし、この自己を正確に認識しないということが、実は社会的動物においては非常に重要な性質になっているように思う。我々人間は他人を通してしか、本当の自分を知ることができない。ゆえに、社会的である必要がある。人間やそして多くの動物が社会を形成するのは、この自己を正確に認識しようとするがゆえなのかもしれない。
自分自身を知りたいがゆえに他者と交わるというアイデアは面白い。コミュニケーションの原点は、他者を知ることではなく自分を知ること。だから他者に自分がどのように写っているのかが気になるのかもしれません。
それから、技術を駆使して徹底的にアンドロイドの表情の変化を人間に似せることに取組んだ末、ニュートラルな見かけに行き着いた点も興味深い。人間は、相手の顔の物理的な形態を読みとっているというよりも、言葉、匂い、雰囲気などあらゆる周辺情報を入手して、それらを自分の記憶データと照らし合わせて似たものを探すようです。さらに重要なのが、その時の感情です。
このような人の様々な想像を反映できるテレノイドのニュートラルな見かけこそがテレノイドのデザインの魅力なのだと思う。あえて似たものを探せば、たとえば、能面が近いかもしれない。
これはまさに私が普段感じていることです。能面にしろ文楽の人形にしろ、その時々に信じられないほどの表情を感じ取ります。表情を読み取るのではなく、表情をこちらが創っているのです。想像力のなせる技です。日本の多くの古典芸能は、観客を選びます。想像できない人は、どれだけ観ても楽しめないでしょう。私が3Gを駆使したようなハリウッドの大作映画を楽しめないのは、想像の余地があまりに小さいからなのかもしれません。
他にもたくさんの洞察に満ちた本ですが、著者である石黒教授のキャラクターもとても楽しめます。5年前に自分に似せて創ったアンドロイドに比べ太ってしまった自分自身をもとに戻すべく、ダイエットして三か月で10Kg体重を落としたり、オタクな研究者の思考パターンがよくわかります。ちょっと変わっているけれど、こういう人が世の中にないユニークな発見をするのでしょう。そういう意味でも面白い本でした。
石黒 浩