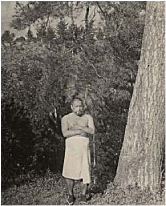日本人は集団主義であり、個人では弱くても組織になると強いという定評がかつてありました。今はどうでしょうか?
ここでいう組織を強くする個人の能力の源泉は、自己を犠牲にしてでも集団のために尽くすという精神と、他者を慮り協調する能力のことだと思います。こういうことは小さい頃から刷り込まれてきています。学校は、基礎知識以外はそれらを学ぶために存在していると言っていいほどです。個性重視の掛け声も、あくまで自己犠牲と協調を乱さない範囲の中での個性だったのではないでしょうか。
大学はどうだったか?それほどの教育方針はなかったと思いますが、モラトリアム期との位置づけで、その間にそれぞれが多くの場合偶然にいろいろな経験(学問はわずか)を積んで、結果として高校までとはやや異なる社会や集団の中で生きる術や自分なりのもの見方や価値観を学んできたような気もします。(最近は就職予備校のようだと聞きますが・・)
そして、就職した企業では。大学時代になんとなく獲得したわずかな価値観を消去して、その企業独自の価値観を一から植え付けることが行われてきました。もちろん、学生時代とは全く異なる社会人としての厳しさはありますが、植え付け自体は高校時代までに戻るようなもので、当初抵抗感はあったとしても、時間とともになじんでいく。それが日本で養成される集団主義の姿でした。
ところが、バブル崩壊後日本企業では、そういった集団主義では組織が持たないことに気づきます。海外企業との競争に勝てないのです。そこで、自律を重視し自立した人材を求めるようになりました。でもそんな人材がどこにいるのか。たとえ社内にいたとしても、組織では異端児です。多くの場合、それまでの文化に適応してしまうか、あるいは適応できずに辞めてしまうかのどちらかです。そもそも特定の個人に期待するのではなく、組織そのものを変えていかなければ無理です。それには時間がかかります。日本はそれに、これまで20年近くの時間をかけてきたといえます。もちろん、全ての企業が一斉にそれに取り組んできたわけではなく、業種によってまだら模様でした。最後に残ったのが電力会社であり、それが変わるきっかけが原発事故というのは、悪い冗談のようです。
学校教育から遡って手をうつ必要があるのは当然ですが、企業は生き残りのためにはそれを待つ余裕はありません。
最も今のビジネスパーソン(「リーダー」だけではありません)に欠けており、かつ必要不可欠な能力は「集団を営む能力」だと考えています。もちろんそれは集団に協調することではありません。自分たちでルールを作って守ったり、相手との関係や集団のあり方に不満がでてきたときに、それを相手や集団に返して議論していく能力です。組織や集団を維持強化することよりも、それらを新たに立ち上げたり、変えていくことのほうが優先順位が高くなっているにも関わらず、それに組織の能力や風土が追いついていない。(大企業の経営会議や取締役会を想像してみてください)
こうした教育は、学校でも企業でもこれまでほとんどなされていませんでした。唯一教育の場として認識されていたのが実践での「修羅場」です。しかし、全てのビジネスパーソンに修羅場を用意することはできません。いかに、修羅場に代わる場を仕組みとして用意できるか。
ここに新たな研修の意味が出てくると考えています。研修の場は、安全が確保されている実験場ともいえます。そこで、自分の善悪や好き嫌いの感覚を見つめて表現し、他者からの反応をもらう。そうした交換作業を通じて、自分がこれまで身につけてきた価値観やものの見方を自覚し、それをより望ましいと考えるものにつくりかえていく。そのプロセスを繰り返す。集団を立ち上げ営むうえで必要不可欠な、自己認識と他者理解、そして他者受用力を、模擬的な相互関係を積む中で獲得していくのです。
集団を乱さず維持していく力から集団を立ち上げ営む力へ、まずは経営層の頭の中から変えていく必要があるでしょう。