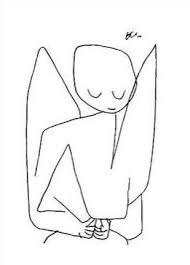幹部候補を対象とした企業研修では、知識の獲得を目的とするものは少ない。知識の多くは、本やネットで容易に獲得できるからです。では、何のためにわざわざ貴重な時間を使って集合研修をするのでしょうか?
私は知識を知恵に変えるためだと思っています。その前に、知識と知恵を定義づける必要があります。「知恵磨く方法」(林周二著)では、こう整理しています。
 | 知恵を磨く方法―――時代をリードし続けた研究者の思考の技術 林周二 ダイヤモンド社 2017-03-16 by G-Tools |
知識とは、僕らが他者から継受した知のことであり、知恵とは、自分自身が自分の体内ないし脳内から生み出した知のことである。(中略)先人たちの知恵=後人にとっての知識、ということになろうか
先人が獲得してきた知恵の集積を、私たちは本などで知識として学ぶことができます。ただそれは借り物にしか過ぎません。インプットした知識を、自分自身の経験などに照らしながら、自分だけの「理論」(マイセオリー)に昇華させることができて、初めて自分が使えそうなものになります。すべからく企業研修の目的は真理の追究ではなく、学んだ知識を適用してビジネスの実践で使えるようにすることです。つまり、知識では意味がなく、そこから知恵を創造させなければなりません。
知識を学ぶことは一人でもできますが、知恵を生み出すのは一人でうんうんうなってできるものではありません。他者との対話によって、知識が自らの経験と紐付きやすくなります。もちろん、最も知恵が生まれるのは実務の現場ではありますが、効率性を高めるため「模擬実践現場」としての研修現場を活用するのです。
また、自分の認識や経験を相対化して再認識することができることも重要です。自分では当たり前だと思っていたことが、他者との対話を通じて実は当たり前ではなかったことに気づくことがあります。もしかしたら職場で上司から「それは違う!」と常々言われていたことかもしれませんが、それが研修という仕事とは(一応)関係ない場(安全地帯)で利害関係のない他の受講者との対話からだったから「気づく」ということが結構あるのです。そうした気づきが知恵を生むきっかけになる、あるいは知恵を生むのに障害となっていた思い込みを除去する効果も期待できます。
したがって、研修の現場ではインプットよりもアウトプットが重要になります。インプットとアウトプットの繰り返しの結果、知恵が創造されるのですから。