広島県福山市の鞆の浦に行ってきました。ご存じの方も多いと思いますが、江戸時代の港が奇跡的に残されている港町です。現在その湊の一部を埋め立て架橋を建設する計画があります。反対運動も盛んですが、どうなるかわからないため今回足を延ばしてきたのです。

古代から海の交通の要衝で、大伴旅人、平家から始まり坂本竜馬、三条実美まで、さまざまな逸話には事欠きませんが、それは別の機会に譲るとして、最近の宮崎駿のエピソードを書きます。今日、聞いたばかりの話です。
最近アメリカでも公開された作品「崖の上のポニョ」の構想を、宮崎監督は、この町の海に突き出た崖の上にある、知人の別荘に二ヶ月間滞在し練ったそうです。今日、その別荘も観てきましたが、眺
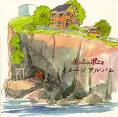 めの良いとても素敵な場所です。
めの良いとても素敵な場所です。
構想を固めた監督は、映画スタッフ200人余りを鞆の浦に集めたそうです。きっと、そのあたりの風景を見せたかったのでしょうが、それだけではありませんでした。
港を見下ろす山の中腹に、沼名前神社があります。そこには、豊臣秀吉が伏見城に造らせた能舞台(重要文化財)が移築され、残っています。その伝統ある能舞台に、監督は近隣からお神楽の一座を招き、実際に奉納神楽を舞ってもらったのです。
今日その舞台にも行ってきましたが、使用していない時は板ですべて覆い隠すということで、舞台は全く見えませんでした。そこを一晩借受け、スタッフ200人のためだけに、本物の神楽を舞わせたのです。(一部の地元民はその御相伴に与ることができたそうで、そのうちの一人の方から直接伺った話です)
直接、映画と御神楽は関係ないと思いますが、映画の舞台(?)となる鞆の浦の町や海、風土をスタッフに理解させるには、きっと欠かせないことだと宮崎監督は考えたのだと思います。
そういえば黒澤明監督は、江戸時代の長屋を舞台とする映画を撮る際、当時人気絶頂だった古今亭志ん生を撮影所に招き、一席噺してもらったそうです。
どちらも、大変贅沢なことで、効率重視では、絶対できないことです。しかし、フィルムには、本物を見せた影響が何らかの形で現れているのでしょう。本物を創るには、本物の力が欠かせないのです。
単純なビジネスベースでは難しいことですが、本物に触れた時間の蓄積というものは、長い目で見たら、人の成長に大きな効果があると思います。
効率に振り回されないで、「眼」に栄養をやることも、忘れないようにしたいと思います。

コメントする